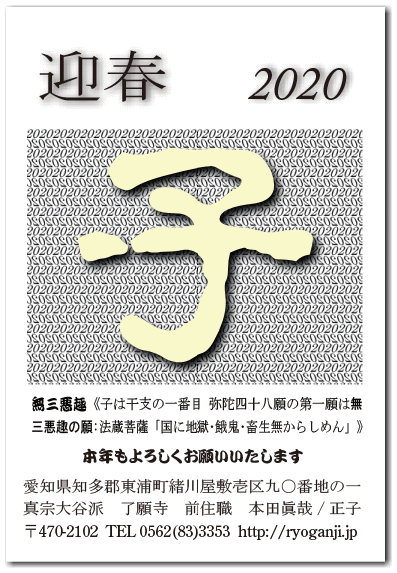
法 話
(226)「
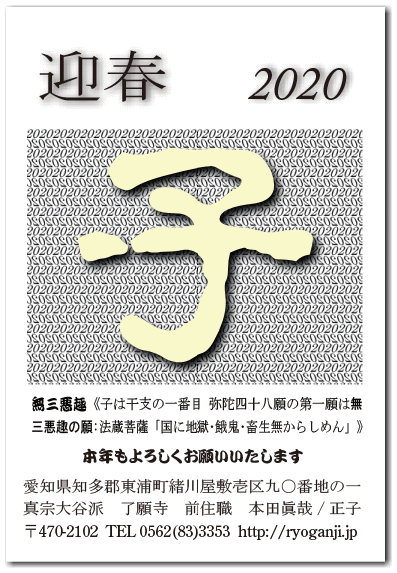 |
「
2020年は
「十二支」とは、子・丑・寅・卯・龍・巳・午・未・申・酉・戌・亥。この十干と十二支を順番に1つずつ組み合わせたものが干支になるのです。例えば、甲と子を組み合わせると、甲子。音読みすると「甲子」になります。高校野球で有名な「甲子園」は1924(大正13)年「甲子」の年に造られたことから命名されたとのこと。
翻って、我が真宗門徒が伝統的に読誦してきた勤行聖典に『正信念仏偈』略して『正信偈』があります。宗祖親鸞聖人のライフワーク『教行信證』行の巻の末に記載されている七言六十句百二十行の偈文。書かれている内容はといえば、本願念仏の教えが釈尊の時代から、七高僧を経て親鸞聖人まで正しく受け継ぎ伝えられてきたことを、深い感動のもと認められた偈。「正信偈」は、親鸞聖人がその感銘を味わい深い詩(偈文)によって、後の世の私たちに伝え示してくださった「いのちの偈」なのです。
因みに、「偈」は漢字の詩句。いわば漢文の歌。これに対して和語(和文)の歌を「和讃」といいます。これまた真宗門徒が勤行時に常用してまいりました。述作は親鸞聖人。『浄土和讃』『高僧和讃』『正像末和讃』の三部があり、称して「三帖和讃」といいます。『浄土和讃』『高僧和讃』は聖人83歳の時に完成。『正像末和讃』は85歳~86歳までの述作と伝えられています。内容は如何となれば、『浄土和讃』では、先ず阿弥陀仏とその浄土を讃嘆。続いて三経和讃。浄土真宗の根本聖典である大無量寿経・観無量寿経・阿弥陀経の三部経を讃嘆。その他の諸経を含めて『浄土和讃』は総計118首。
次に『高僧和讃』。親鸞聖人が真宗相承の師と仰ぐ三国の七高僧の行徳を賛嘆した述作。七高僧とは、印度の龍樹菩薩(AD150~250頃)・天親菩薩(5世紀)、中国の曇鸞大師(AD476~542)・道綽禅師(AD562~645)・善導大師(AD613~681)、そして日本の源信僧都(AD942~1017)・源空聖人(AD1133~1212)。全117首。七高僧について『正信偈』には、
(前略)印度西天之論家
中華日域之高僧
顯大聖興世正意
明如來本誓應機(後略) と謳われています。
第三帖目は『正像末和讃』。先ず、「正像末」とは何ぞや? 正法・像法・末法の“三時”のこと。釈尊が入滅されてから時代が下るにしたがって、法はあっても実践は形ばかりになって悟ることができず、ついには実行されなくなるとする歴史観に基づく時代区分。一説には、正法:教・行・証全てが備わっている時代(釈尊滅後500年)。像法:教・行のみの時代(正法後1000年)。末法:教のみの時代(像法後10000年)。1052年(永承7年)を末法の第1年とする末法思想が平安貴族社会に流布し、人心不安を招いたとか。
折しも、聖道自力の諸教が次第に衰えるのに対して、親鸞聖人は阿弥陀仏の他力信心を、いよいよ時機相応の教えであることを114首の『正像末和讃』をもって讃嘆されたのです。
正像末の三時には
弥陀の本願ひろまれり
像季末法のこの世には
諸善竜宮にいりたもう
話が遠回りしてしまいましたが原点に返りましょう。『佛説無量壽経』には、阿弥陀仏がまだ法蔵菩薩として修行していた因位のころ、仏になる条件として四十八の誓いの願を建てられました。前述の『正信偈』には、
(前略)法蔵菩薩因位時
在世自在王佛所
覩見諸佛浄土因
國土人天之善悪
建立無上殊勝願(後略)
その四十八願の第一番目、第一願は「無三悪趣の願」。「三悪趣」とは「三悪道」ともいい、詳しくは地獄・餓鬼・畜生。大無量寿経の願文は「説我得佛 國有地獄餓鬼畜生者 不取正覺」。読み下すと「説い我仏を得んに、国に地獄・餓鬼・畜生有らば、正覚を取らじ」。いうまでもなく、この誓願を建てられたのは法蔵菩薩。“菩薩”は仏に成る前の「因位」の時。三悪趣を無くそうと願われ、もしできなければ正覚を取らない、「果位」の仏に成らないと誓われたのです。なお、この三悪趣は物語の世界では無く、目に見えないけれども我々の周囲にある、人間世界の有様そのものである、と法蔵菩薩は仰ったのではないでしょうか。
そしてその願成就し、法蔵菩薩は阿弥陀仏となられました。成就した願は衆生に「南無阿弥陀仏」の名号として廻施されたのです。この名号、我が真宗の本尊であり信心の要であります。他宗派においては、各寺々々でご安置する本尊が異なっているケースがあるようです。例えば、大日如来・釈迦牟尼如来・観世音菩薩・阿弥陀如来・曼荼羅・弥勒菩薩・勢至菩薩 等々。真宗の本尊は阿弥陀如来。「真宗大谷派宗憲」(宗派の憲法)第9条には「本派は、阿弥陀如来一仏を本尊とする」と謳われています。
干支の第一番目の「子」に、尊い阿弥陀仏の第一番目の願「無三悪趣の願」を引き合いに出し、私見を述べさせていただきましたこと,失礼千万とお叱りを受けるか、と。ご批判はごもっとも、甘受させていただきます。ご笑殺ください。
合掌
《2020/1/3前住職・本田眞哉・記》